📘 最も画数の多い漢字
筆画(ひっかく)・画数・筆順について
筆画(ひっかく)とは、漢字を形づくる最小の単位です。 1回筆を紙に下ろしてから離すまでに書かれる「線」や「点」のことを指します。
この筆画の数を画数(かくすう)と呼び、「1画」「2画」…のように数えます。 また、どの順番で筆画を書いていくかを筆順(ひつじゅん)といいます。
-
- 筆画=漢字を構成する最小単位。1回の運筆でできる線や点。
-
- 画数=筆画の総数。1画・2画…と数える。
-
- 筆順=筆画を書く順序。可読性・書写の効率に関わる。
筆画の種類
「永字八法(えいじはっぽう)」は、書道を学ぶ人が最初に習う、漢字の基本筆法の集大成です。 一つの「永」という字の中に、漢字を構成する8つの基本筆画がすべて含まれているという、実に巧妙なシステムなんですよ。
具体的には、側(ソク:点)、勒(ロク:横画)、努(ド:縦画)、趯(テキ:はね)、策(サク:短い右上がりの横画)、掠(リャク:左はらい)、啄(タク:短い左はらい)、磔(タク:右はらい)の8つです。 ただし、これはあくまで書法上の説明であり、筆画そのものを厳密に分類したものではありません。
- 側(ソク) - 点(丶)
「永」の最初の点。書道では「石が転がり落ちる勢い」と表現されます。筆を斜めに入れ、軽く止めてから引き上げるのがコツ。ただの点に見えて、実は最も難しい筆画とも言われます。 - 勒(ロク) - 横画(一)
右上がりの横線。馬の手綱を締めるように、力強く引きながら書きます。始筆と終筆に気を配り、緩急をつけるのがポイントです。 - 努(ド) - 縦画(丨)
弓を引くような緊張感のある縦線。真っ直ぐに見えて、実は微妙に左に膨らませるのが伝統的な書き方。自然な流れで書くことが大切です。 - 趯(テキ) - はね(㇂)
縦画の終わりの部分。筆を一旦止めてから、勢いよく跳ね上げます。武士が刀を振り上げるような鋭さが求められます。 - 策(サク) - 短い右上がりの横画
馬を鞭で打つような短く鋭い線。軽やかさと力強さを両立させる筆画です。 - 掠(リャク) - 左斜めはらい(丿)
女性の長い髪が風になびくような優雅な曲線。一息でなめらかに払うのが理想です。 - 啄(タク) - 短い左斜めはらい
鳥がくちばしでついばむような鋭い動き。短くても勢いと方向性が大切です。 - 磔(タク) - 右斜めはらい(㇏)
最後の大胆な払い。刀で切るような勢いが必要で、書き終わりまで気を抜けません。
面白いのは、これらの筆画が単なる線の種類ではなく、それぞれに自然の動きや物の様子が喩えられている点です。書道家はこれらの筆法をマスターするために、何年も「永」の一字を書き続けると言います。
「永字八法」は単なる書き方のルールではなく、漢字の美しさの本質を伝えるための知恵なのです。一見単純な線の集まりに見える漢字も、実はこんなに豊かな表現が詰まっているんですね。
現代の筆画分類
現代ではもっと細かく分析されていて、中国では約30種類の筆画に分けられています。基本は次の8種類です。
- 点(丶) → ポンっと打つ点
- 横(一) → まっすぐな横線
- 竪(丨) → まっすぐな縦線
- 提(㇀) → 右上にはねる線
- 撇(丿) → 左にサッと払う
- 捺(㇏) → 右にグイッと払う
- 鉤(亅) → フックのように曲がる
- 折(𠃍) → クイッと折れる線
これらを応用して複雑な筆画が説明されます。例えば、「乃」の右側の部分は「横折折折鉤」と分解され、このように筆画を組み合わせることで偏や旁といった部首や字形が作られていきます。
漢字を書くとき、無意識にやっているこの「線の書き方」、実は長い歴史としっかりしたルールがあったんですね。次に字を書くときは、ぜひ自分の手の動きを観察してみてください。きっと新たな発見がありますよ!
最も画数の多い漢字とは?
漢検準1級に配当されている漢字の中で、最も画数が多いのは
「鬱」(29画)です。
この字は「難しい漢字」の代表格として広く知られています。
例えば、阿辻哲次氏の著書『教養の漢字学』のまえがきでも、
「『鬱』なんて難しい字はいったいだれがどのようにして作ったのだろう」と触れられており、
学習者が素朴な疑問を抱く典型的な漢字として紹介されています。
さて、少し視野を広げて、漢検の範囲を離れ、JIS漢字全体の中で
もっとも画数の多い漢字を見てみましょう。
それが 「鸞(らん)」 と 「驫(ひょう/とどろき)」 の2字で、
いずれも 30画 です。
- 鸞(らん):伝説上の霊鳥を表す字。漢検1級に配当され、小学生向けの塾でも取り上げられることがあります。
- 驫(ひょう/とどろき):「馬」が三つ並んだ形の字。青森県西津軽郡深浦町には、 実際に 「驫木(とどろき)駅」 という地名に使われています。 ただし、漢検の出題範囲には含まれません。
補足すると、JIS漢字に含まれる字の画数は30画が上限であり、
「鸞」と「驫」がその代表例です。
つまり、日常で目にする可能性がある漢字の中で、これ以上画数が多いものは存在しません。
漢字検定(漢検)1級の画数トップとその他の最長画数の漢字
ここで再び漢字検定(漢検)の範囲に戻ってみましょう。
合格率は7分の1以下という漢検1級の出題漢字の中で最も画数が多いのは、33画の漢字
『麤』 です。
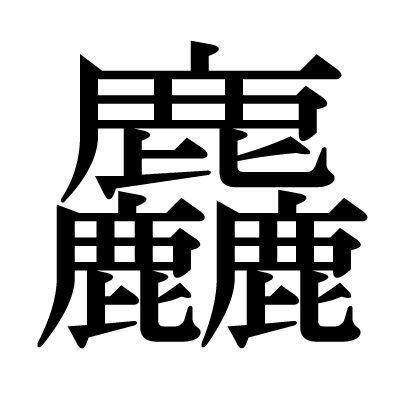
音読み:ソ、訓読み:あら(い)・おお(きい)・ほぼ・くろごめ
他字体・異体字・同字としては 『麁』 があります。
この漢字を含む四字熟語には 「麤枝大葉(そしたいよう)」 があり、 「細かい規則にこだわらず、自由に筆を振るって文章を書くこと」を意味します。
その他の字書・辞典でのトップ画数
-
小学館『新選漢和辞典』
画数最長:30画
「驫(ひょう)」…多くの馬を表す
「鸞(らん)」…鳥の一種を表す -
講談社『新大字典』
音読み:トウ・ドウ
画数:48画
漢字:龘
解説:本来は「龍」を3つ重ねた形。俗に「雲」を2つと「龍」を3つ組み合わせた形で、人名漢字として使われていた説があります。読みは一般に「たいと」や「おとど」、意味は「龍が行くさま」。 -
『大漢和辞典』
画数最長:53画
漢字:𬚩 -
六十四画の漢字
1つ目:音読み「テツ・テチ」、意味「言葉が多い。多言。」

2つ目:音読み「セイ」、意味は未詳

-
国字(日本で作られた漢字)の最高画数
画数:84画
「おとど」「たいと」「だいと」と読む漢字で、雲を3つと龍を3つ組み合わせたもの。現在は「幻の漢字」とされています。

雲(☁)3つと龍(龍)3つを組み合わせた日本製漢字
「おとど」「たいと」「だいと」と読みます補足:国字とは、日本で独自に作られた漢字を指します。中国由来の漢字に対して、日本で創作された文字のことです。例として「峠(とうげ)」「畑(はたけ)」「榊(さかき)」「辻(つじ)」などがあります。
小学生の漢字画数
小学生で学ぶ漢字の中で、学年ごとの画数の最も多い漢字をまとめると次の通りです。
-
小学1年生:森(12画)
1年生の漢字の平均画数は約5画なので、2.4倍にあたります。 -
小学2年生:顔・曜(18画)
「森」の1.5倍で、2年生にとってはかなり複雑な漢字です。 -
小学3年生:題(18画)
画数は2年生と同じです。 - 小学4年生:議・競(20画)
- 小学5年生:護(20画)
-
小学6年生:警・臓(19画)
やや減少します。
中学校以降(漢字検定を目安に)
中学校では学年ごとの学ぶ漢字は明確ではありませんので、漢字検定(漢検)の級で確認します。
-
漢検4級:鑑(23画)
これまでの記録を大きく上回ります。 - 漢検3級:顧・魔(21画)
-
漢検2級:艦(21画)
常用漢字範囲内ではこれが最高画数です。
結論として、小学生から漢検2級までの範囲で、23画が最も画数の多い漢字となります。
-
小学1年生:森(12画)