📘 漢字の成り立ちと漢字の種類
4種類の漢字の違い~象形文字・指事文字・形声文字・会意文字
- 「指で表すから、指事文字:しじもじ」
- 「もののかたちをかたどった、象形文字:しょうけいもじ」
- 「音が関係するから、形声文字:けいせいもじ」
- 「意味を合わせるから、会意文字:かいいもじ」
漢字の成り立ち方には、2つのポイントがあります
その漢字が- 2つ以上の部分に分解できるか、分解できないか
- 絵で描けるか、描けないか
指事文字と象形文字の違い
象形文字と指事文字の違いは簡単です。
漢字を「分解できない」「分解できる」の2つに分類してみると、
- 分解できる文字⇒形声文字か会意文字
- 分解できない文字⇒指事文字か象形文字
- 指事文字⇒抽象的
- 象形文字⇒具体的
象形文字
象形文字とは、日・月などのように、事物の形を描いて簡略化した絵文字。
例・・・
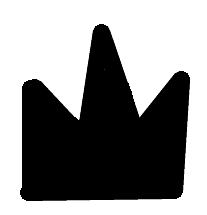 ⇒
⇒  から山という字ができました。
から山という字ができました。
このように物の特徴を簡単に絵に表現し、この絵をもとに作られたのが象形文字です。
動画で見る漢字の成り立ち
指示文字
指示文字とは、形で表しにくい物を点や線を使ったり象形文字に印をつけたりして表した文字。
絵としては描きにくい一般的な事態を、抽象的な約束や、印であらわした字。
一・二・三などの数字や、平面上に-印をつけた上や、平面の下を-印で示した下なども指事文字。
指事文字の見分け方はコチラ
指事文字・指示文字の完全解説
例・・・
![]() ⇒ 上 です。
⇒ 上 です。
もとになる線の上に印をつけ上を表した文字です。
象形文字と指事文字の二種がすべての漢字の基本になります。
動画で見る漢字の成り立ち
会意文字
会意文字とは、二つ以上の漢字を組み合わせて、別の新しい意味を表したものです。
象形文字や指事文字(文)を組み合わせて、さらに複雑な意味を表そうとしたで、武(戈+止)や、信(人+言)などの文字です。
例・・・
口 と 鳥 で 鳴 になります。
鳥が口で音を出すことを表して鳴という漢字になります。
動画で見る漢字の成り立ち
形声文字
「意味」を表す部分と「音」を表す部分が合わせてできた漢字です。
形声文字は、たくさんあって、漢字のほとんどがこれにあたります。
「シ(さんずい)+音符 工」→江や、「シ(さんずい)+音符 可」→河のように、片側に発音を表す音符(つまり意味を表す言葉)を含み、他方にそれが何の事態に関係するかを示す偏をそえたものです。
漢字全体の七~八割はこれに属します。
例・・・
シ と 羊 で 洋 になります。
シは水を表し羊は「ヨウ」
会意文字と形声文字の二種は、文から派生しふえたので、字といいます。
「字」は、「孳」・「滋」(ふえる)と同じような意味です。
動画で見る漢字の成り立ち